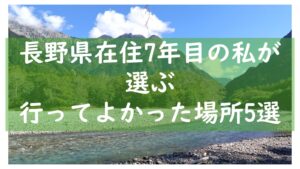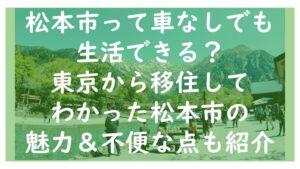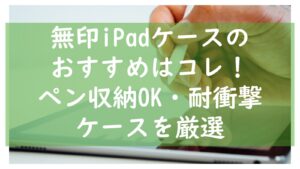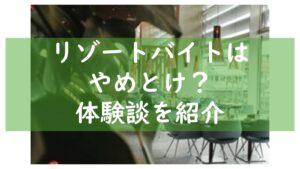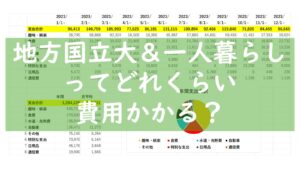※本ページはプロモーションが含まれています※
大学院生なのに英語ができない…それでも大丈夫?現役博士大学院生が解説
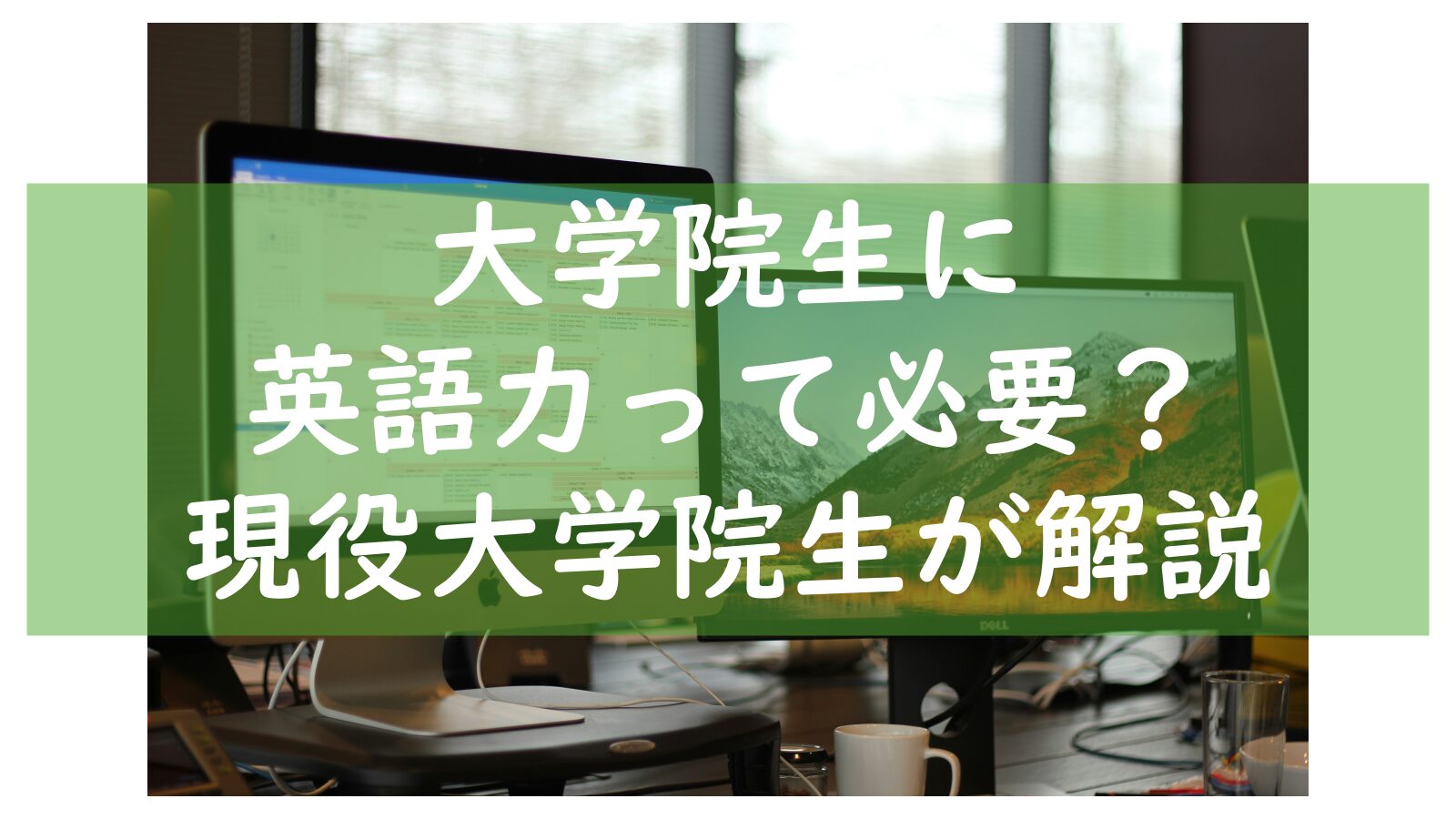
- 大学院に進学したい!
- 英語全然できないんだけど、大丈夫?
- どう対策すればいい?
- 経験者さん、教えて!
大学院って英語できなくても大丈夫?
結論:英語ができなくても、
なんとかなる。
それより結果を出すことのほうが
ずっと大事。
⇛英語力はそんなに重要じゃない
⇛研究がんばるほうが大事
⇛そのために必要なのは、同僚・先輩・指導教員とのコミュニケーション
⇛英語力はその後、必要に応じて身につけていけば良い
大学院に進学すると、避けて通れない話題の一つに「英語力」がある。
「論文は英語が多いから読めるようにしておいたほうがいい」「英語で発表できないと将来困る」
――そんな声を聞いて、不安を感じている人も多いのではないだろうか。
たしかに、英語は研究活動において一定の役割を果たしている。しかし、果たして大学院生にとって英語力は絶対に必要なのだろうか。
 トットマン
トットマン私は博士課程に在学中の現役大学院生である。
本記事では、実際に大学院で研究生活を送る筆者の視点から、「英語力の必要性」について現実的な立場で考察してみたい。
↓おすすめはAI英会話アプリ!↓


\ 詳細はこちらから! /
\ 音声配信でも喋ってるよ /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
大学院生なのに英語ができない…それでも大丈夫?
結論:英語力は「なくてもなんとかなる」
結論から言うと、「英語力はなくてもよい」と私は考えている。
もちろん、英語力があればそれに越したことはない。



しかし、本質はそこではない。
たとえば、「大学院生に英語力は必要か?」という問いは、プロ野球の2軍にいる選手が「自分、メジャーリーグを目指したいんだけど、英語力って必要ですか?」と尋ねているようなものだと感じる。
それよりもまずは目の前の課題、つまり「野球を上手くなること」に集中すべきである。
大学院も同じ。まずは研究に集中すべきであり、英語力を気にするのはその後でもよい。
↓おすすめはAI英会話アプリ!↓


\ 詳細はこちらから! /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
\ 音声配信でも喋ってるよ /
大学院で英語ができなくても大丈夫な理由
ここからは、私が思う大学院で英語ができなくてもなんとかなる理由を解説していく。
理由1:論文はGoogle翻訳で十分読める
理由の1つめは、英語論文はGoogle翻訳で十分読めるから。
研究をするにあたってはほぼ100%論文を読まなければならず、信頼のおける論文のほぼ100%は英語。
そういう意味では、確かに英文の読解力は必要かもしれない。
しかし、今どきGoogle翻訳やAI機能を使った翻訳機能などありふれまくっている。
実際のところ、私だってほぼ論文を英語のままで読んでいない。Google翻訳とかDeepLを使って日本語にしてから読んだほうが速いから。
私はこれまで数多くの論文を読んできたが、Google翻訳でも内容は十分に理解できる。というかむしろ英語で頑張って読むより圧倒的に理解が速い。
それに、これは後述するが、



論文を読む目的は「情報収集」であって、「長文読解」ではない。
要するに、必要な情報を得られりゃそれでいいのである。それが日本語か英語かなんて大した問題じゃない(原文は英語のもののほうがよい)。



もちろん、英語のまま読む方がニュアンスを正確に掴めることもある。
たとえば、私が研究を進めていく中で論文中の「modification」という単語の解釈に難儀したことがある。
辞書的には「修正」とか「修飾」という意味なのだが、その論文中では「改変」と訳されていた。
論文中でこれを「修飾」と解釈するのか「改変」と解釈するのかでは、意味が大きく異なる。
「修飾」だとなんとなく外側だけを変えるイメージだが、「改変」だと内側から思いっきり変えるようなイメージがある。
細胞に例えるなら、細胞の外側をいじったのか、内側をいじったのかという違いになり、だいぶ解釈が変わってきてしまう。
こういったときは文脈で判断する必要があるので、確かに英語力はあった方が良い。
しかし、こういった例は膨大な論文の中でもほんの数回程度であり、そのために全てを英語で読み込む必要があるかといえば、私はそうは思わない。
理由2:母国語の利便性は第二言語に到底及ばない
理由の2つめは、母国語の利便性は第二言語に到底及ばないから。
どれだけ第二言語(例えば英語)をめちゃくちゃ勉強しても、母国語(我々日本人でいう日本語)の利便性に第二言語が勝つことはないと私は思っている。
それを実感した私のエピソードを紹介したい。
以前、私のいる研究室に中国出身の先輩がいた。
その方は10歳の頃に来日し、以降20年以上ずっと日本で生活しており、日本語はほぼネイティブレベルだった。



最初にお話したときは、途中まで本気で日本人だと思っていたくらいだ。
しかし、研究などの難しいやりとりは中国語の資料を読まれていることが多く、LINEも中国語でされていることも多かった。
ふと気になって、



「やっぱり日本語より中国語のほうが得意なんですか?」
と聞いてみたところ、
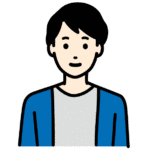
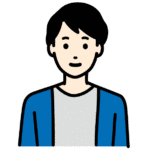
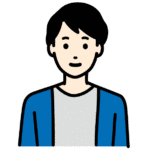
「あったりまえじゃん(笑)」
と流暢な日本語で返されたことがあった。
たまたまその人がそうであっただけかもしれないが、異国の地に20年以上住んでいてネイティブレベルの言語力を持っている人でさえ、やっぱり母国語のほうが便利なのだと実感した。
ただでさえ英語力の乏しい我々日本人なら、尚更である。
理由3:大学院で必要なのは「結果」である
理由の3つめは、大学院で必要なのは結果であって必ずしも英語力ではないから。
例えば、論文を読む理由は、長文読解を練習するためではない。自分に必要な情報を得るためである。
似た研究があるか、参考になるプロトコルがあるか、引用に使えるデータはないか、そういった視点で論文を探しているのであって、英語力を鍛えることが目的ではない。



それよりもまず大切なのは、「結果を出すこと」である。
そのために重要なのは、指導教員とのコミュニケーションだ。
大学院生がゼロから研究を組み立てるのは難しいが、指導教員は多くのアイデアや方向性を持っている。
彼らと密に連携を取り、進捗や悩みを共有しながら研究を進めていくことこそ、成果につながる一歩である。
↓おすすめはAI英会話アプリ!↓


\ 詳細はこちらから! /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
\ 音声配信でも喋ってるよ /
留学するなら英語力は必要
もちろん、留学を目指すのであれば話は別である。
入学時点で英語力を問われることが多く、そこで初めて本格的に英語学習に取り組む必要が出てくる。



しかし、それは「必要になってからやればよい」のである。
そもそも英語力以前に、研究成果をろくに挙げられていない外国人をわざわざ採用したいと思う研究室は地球上に1つもないだろう(個人の見解です)。
繰り返しになるが、まずは結果を出すこと。



そのための手段として、英語力は決して必須ではない。むしろそれより先にすべきことがある。
というのが私の考えだ。
↓おすすめはAI英会話アプリ!↓


\ 詳細はこちらから! /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
\ 音声配信でも喋ってるよ /
最後に
今回の話は、「大学院に入る時点で英語力がなければダメなのか?」という不安を持つ方に向けての私なりの答えである。
英語力があるに越したことはない。だが、それよりもまずは自分の研究に集中し、日々手を動かし、結果を出すこと。
そして、指導教員との信頼関係を築くことが、何よりも大切であると私は考えている。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いである。
↓おすすめはAI英会話アプリ!↓


\ 詳細はこちらから! /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
\ 音声配信でも喋ってるよ /