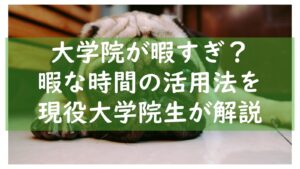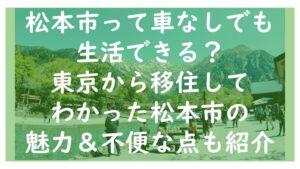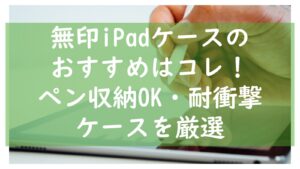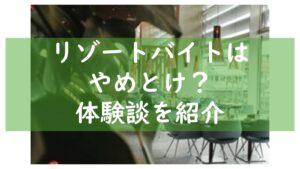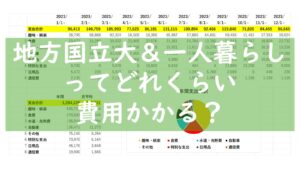※本ページはプロモーションが含まれています※
大学院生活の辛いところとその対処法を現役博士大学院生が解説
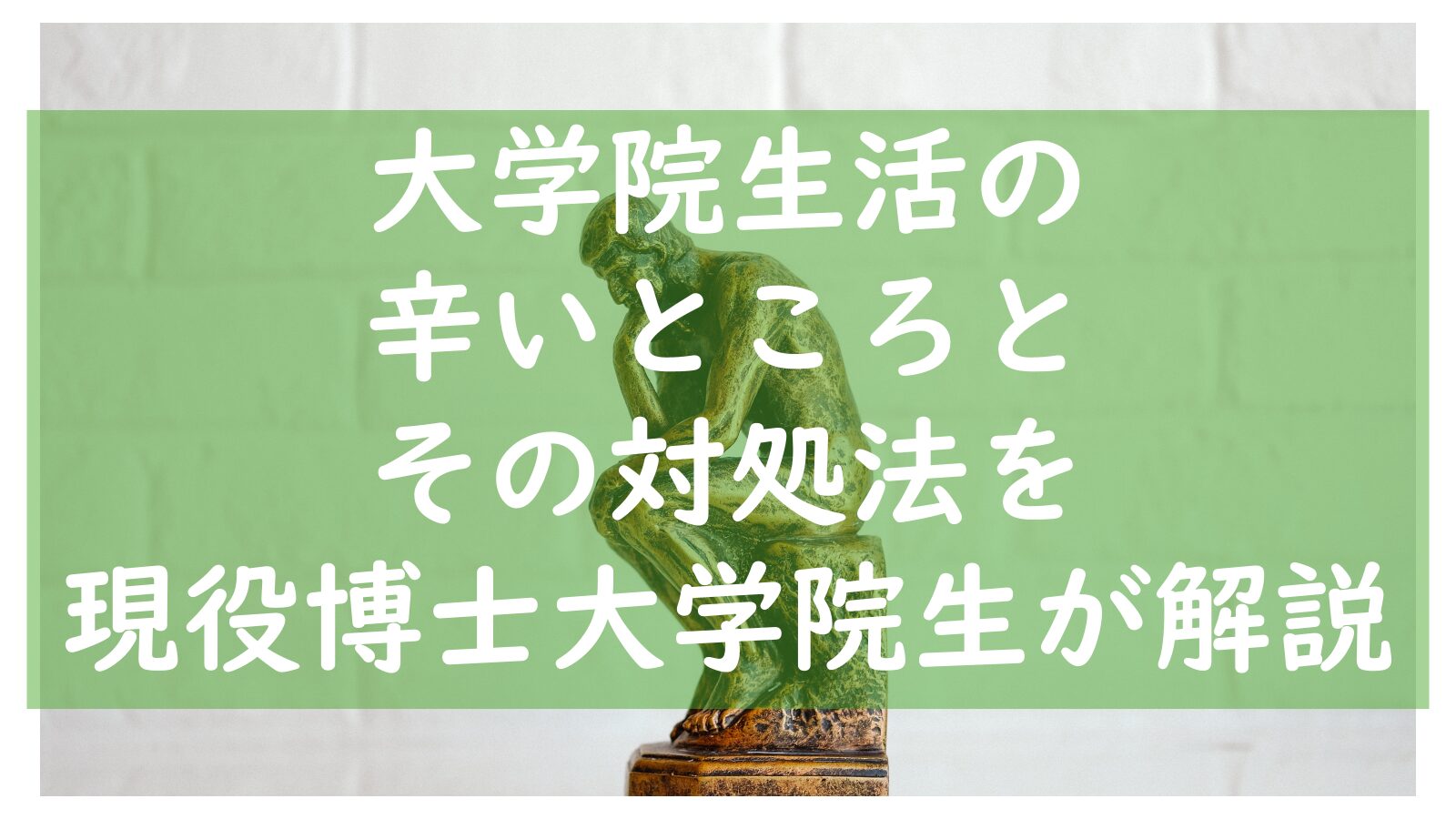
- 大学院が辛い…
- みんなこんなもんなのかな?
- どうやって対処すればいい?
- 経験者さん、教えて!
大学院生活の辛いところと
その対処法
大学院生活の辛いところ&対処法
✓批判・否定と向き合わなければならないところ
(対策)⇛批判・否定があってこそ研究であると考える
(対策)⇛ChatGPTにアドバイスを請う
✓成果主義でプレッシャーを感じやすいところ
(対策)⇛プレッシャーがあったほうがむしろ人生は充実する
✓生活が不規則になりやすいところ
(対策)⇛「研究室に行く」というルーティンは崩さない
大学院というと自由度が高く、やりたい研究に没頭できるという良い面がよく語られるが、実際にはしんどい部分もある。
 トットマン
トットマン私は医系大学院に所属する現役博士大学院生である。
今回はそんな私から、私自身が感じている大学院生活の辛さと、それに対する考え方・対処法をまとめてみた。
\ 音声配信でも喋ってるよ /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
大学院生活の辛いところ&対処法
1. 批判・否定との戦い
大学院で研究を進めていくと、必ず批判や否定に直面する。
指導教員やその他教授陣の方々から「そのデータは本当に正しいのか」「論理が飛躍していないか」「根拠はどこにあるのか」など、鋭い指摘が飛んでくる。



自分では筋道を立てて進めているつもりでも、他者からの目で突っ込まれると落ち込むことも少なくない。
対処法
だが、少し真面目な話にはなるが、批判があるからこそ研究は研究たり得るのだと私は考えている。



人気漫画「チ。地球の運動について」のなかにこんなシーンがある。
地動説を唱える天文学者であるバデーニは、とある事件がきっかけで自分で得た研究結果を誰にも渡さず独占しようとする。
その行動に対する同行者であるオグジーとの対話なのだが、
オグジー「あまり他人を排除しすぎると間違いに気づきにくくなるのでは?それは研究にとって良くないんじゃ」
オグジー「自らが間違ってる可能性を肯定する姿勢こそが学術とか研究には大切なんじゃないかってことです。第三者による反論が許されないなら、それは信仰だ。信仰の尊さは理論や理屈を超えたところにあると思いますが、それは研究と棲み分けられるべきでは?そして、反論してもらうには他人が重要なので、あまり排除するのは」
バデーニ「大まかには理解した。だが、同意はしない。その話は大変危険だ。その姿勢を研究に採用してしまうと、我々は目指すべき絶対真理を放棄することになる。そして学者は永遠に未完成の海を漂い続ける。その悲劇を我々に受け入れろと?」
オグジー「そうです。それでも、間違いを永遠の正解と信じ込むよりましでは?」
「チ。地球の運動について 第12話より」
誰からも疑われず、検証もされないものは「信仰」に近く、学問とは呼べない。
批判を受け止め、自分の研究をより良いものにしていく姿勢が研究を研究たらしめるうえで大切だと私は感じている。
また、私がよくやる実践的な対処法としては、ありきたりで今風ではあるが「ChatGPTに聞く」こと。
議論で詰まったときに、「相手はこういう意図で言っているのでは?」といったヒントをもらえるのはとても助けになる。



私も実際、指導教員とのやり取りの中で「この人は何を言ってるんだ?」「何を私に期待しているんだ?」とわからなくなることがある。
そのときも、それをChatGPTにそのままぶつけて「あぁ、そういうことか」と合点がいきそこからの流れがスムーズに行くことがよくあった。
もちろん鵜呑みにせず自分で調べ直す必要はあるが、批判への返し方のアイデアを得る上ではかなり有効である。
2. 成果主義のプレッシャー
大学院には期限がある。
修士なら2年、博士なら3年以上。その中で成果を出すことが求められる。



例えば私の場合2か月に一度、週に一度の指導教員とのMTGとは別に、研究チームの先生に進捗を報告しなければならず、そのたびにプレッシャーを感じる。
時には「もっと早くやれ」「これをいつまでにやれ」と無理難題を言われることもあるが、それも研究の現場ではよくあることである。
対処法
対処法としては、私は「プレッシャーがあるからこそ人生は充実する」と考えるようにしている。



もちろん強すぎればしんどいが、全くストレスのない生活は逆に退屈であろう。
適度なプレッシャーを前向きに受け止めることが、研究を続けるうえでの原動力になると思う。
3. 生活リズムが乱れやすい
大学院は会社のように「9時出勤、18時退勤」といった明確なルールがないことが多い。
研究室によっては自由に来て帰れるため、どうしても生活リズムが不規則になりやすい。



私自身も、午前中は家で作業して午後から研究室へ行く日もあれば、追い込み時期は朝4時半に研究室に行くこともある。
逆に深夜2〜3時まで残る日もあり、生活はどうしても乱れがちだ。
対処法
そこで意識しているのが「平日は必ず研究室に行く」というルール。
どんなに気分が乗らない日でも、とりあえず研究室へ行くようにしている。
外に出るだけで気持ちが切り替わり、研究に取り組む姿勢も整いやすいからだ。
研究室に来なくなって、精神的に追い込まれて研究が続かなくなる人もそれなりに見てきたので、自分なりに守っている習慣である。
なんでもいいので、これだけは必ず守るというルーティンを自分の中に持つことが大切だ。
\ 音声配信でも喋ってるよ /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /
まとめ
大学院生活には「批判との戦い」「成果主義のプレッシャー」「生活リズムの乱れ」といった辛い面がある。
ただ、それぞれに向き合い方や工夫を持つことで、前向きに研究生活を続けていけると感じている。
これから大学院を目指す方や、今まさに大学院で奮闘している方の参考になれば嬉しい。
大学院生活の辛いところと
その対処法
大学院生活の辛いところ&対処法
✓批判・否定と向き合わなければならないところ
(対策)⇛批判・否定があってこそ研究であると考える
(対策)⇛ChatGPTにアドバイスを請う
✓成果主義でプレッシャーを感じやすいところ
(対策)⇛プレッシャーがあったほうがむしろ人生は充実する
✓生活が不規則になりやすいところ
(対策)⇛「研究室に行く」というルーティンは崩さない
\ 音声配信でも喋ってるよ /
大学生・大学院生が今すぐ
登録すべき就活サイト3選
【1位】アカリク


研究と就活を両立できる理系・大学院生向けスカウト型就活サービス
登録するだけで、研究を活かせる専門職のスカウトが届く!
大学院出身のコンサルタントによる就職支援や、内定直結の選考イベントも充実!
\ 無料登録はこちらから! /
【2位】OfferBox


オファー型就活サイトの決定版!
大手・官公庁を含む17,000社以上が利用中。
適性診断や動画プロフィールで“人となり”を伝えられる、新しい就活スタイル!
\ 無料登録はこちらから! /
【3位】ABABA


最終面接の経験を次につなげる新しい就活サービス
最終面接まで進んだ実績をもとにスカウトが届く、日本唯一のプラットフォーム!
LINE連携で手軽にやり取り、登録・利用はすべて無料!
\ 無料登録はこちらから! /